この記事を読むとわかること
- 映画『隣のステラ』に込められた制作陣の想い
- 監督・脚本・音楽など各スタッフのこだわり
- “王道だけど新しい”青春恋愛映画の魅力
映画『隣のステラ』スタッフ・監督情報|フジテレビ制作陣の想いを伝える本記事では、若き才能が集った制作舞台裏や、監督・プロデューサーが抱いた情熱を余すところなく紹介します。
原作漫画の空気感を映像に落とし込むため、監督・松本花奈をはじめ、脚本、音楽、編集など各スタッフがどんな思いで携わったのか。フレッシュな制作陣の核心に迫ります。
“近くて遠い”幼なじみの恋を描いた本作が、どうして青春の胸キュンを真っ直ぐに届けることができたのか。その秘密はまさにここにあります。
監督・松本花奈が描いた“原作の世界観をそのままに”
映画『隣のステラ』の監督を務めたのは、若干10代での長編映画監督デビューを果たした松本花奈さんです。
映像業界では珍しい若手女性監督として注目されてきた彼女が、本作にどう向き合い、どのように“原作の世界観を損なわずに映像化”したのかが、作品のクオリティを大きく左右しています。
高校生の淡い恋心や、幼なじみ同士の距離感というテーマをリアリティを持って描けるのは、監督自身が“若者の空気感”を体感してきたからこそ。
10代での長編監督デビューからの成長
松本花奈監督は、映画『脱脱脱脱17』で長編映画の世界に飛び込み、注目を浴びました。
以来、ドラマ・CM・MVなど多様なジャンルを経験しながら、映像表現の幅を広げてきました。
“登場人物の心理に寄り添う”という演出スタイルが定評を得ており、本作でもその手腕が存分に発揮されています。
原作の雰囲気を映像化する演出への意図
原作は餡蜜さんによる人気恋愛漫画であり、その絵柄や間の取り方がファンに支持されています。
監督はその“間”を映画にどう落とし込むかを考え、テンポの緩急や無音の使い方などに細やかなこだわりを見せました。
「登場人物の沈黙が語ること」を大切にした演出こそが、観る者の心に残るラストシーンへとつながっています。
脚本・川滿佐和子が紡ぐ“誰もが共感できる初恋の距離感”
映画『隣のステラ』の脚本を担当したのは、川滿佐和子(かわみつさわこ)さん。
テレビドラマやWEBドラマなどで注目される新進気鋭の脚本家で、人物の繊細な心理描写や、リアルな会話劇を得意とすることで知られています。
今回の作品では、原作の持つやわらかくも切ない空気を壊すことなく、実写として自然に馴染ませる脚本が高く評価されています。
映像化にあたっての世界観の設計
原作『隣のステラ』は、日常と非日常が交差するような不思議な空気感が魅力ですが、それを実写で再現するのは決して容易ではありません。
川滿さんは、“セリフの間”や“視線のすれ違い”など、表現しにくい感情の距離感を脚本に落とし込むことにこだわったとされています。
特に、ステラと真臣の間にある“踏み出せそうで踏み出せない一歩”をどう描くかに心を砕いたことが、登場人物の関係性に説得力を与えています。
登場人物の心情の機微を台詞に乗せる工夫
本作では登場人物の心情をストレートに語らせるのではなく、さりげない言葉選びや行動の積み重ねによって表現しています。
例えば、真臣がステラに対して“何も言わない優しさ”を選ぶシーンや、ステラが“笑ってごまかす”場面は、脚本における心理の裏打ちがあってこそ成立しています。
観客が「自分の初恋を思い出した」と感じる理由は、まさに川滿さんの手腕によるものです。
制作陣が語る“フレッシュでまっすぐなラブストーリー”への挑戦
『隣のステラ』が観客の心をとらえる理由は、「王道ラブストーリー」を真正面から描く姿勢にあります。
その背景には、プロデューサーを務めた岡田翔太さんや原作者・餡蜜さんの“ストレートな想い”が込められています。
一見するとよくある幼なじみの青春恋愛。しかしその中に込められた細部のこだわりと温度感が、観客の共感を生み出しているのです。
原作者・餡蜜の“妄想から始まった”創作の喜び
餡蜜さんは『隣のステラ』について、「自分の好きな要素をとにかく詰め込んだ」と語っています。
“幼なじみ” “クールなヒーロー” “お節介なヒロイン”という王道設定は、まさにその結晶です。
映像化にあたっても餡蜜さんは「自分のキャラたちが動いてしゃべるのを見るのが楽しみ」とコメントしており、制作陣への信頼が感じられます。
プロデューサー・岡田翔太がこだわった“王道ラブの構造”
岡田翔太プロデューサーは、「いまの時代に“直球の恋愛映画”を作ることにこそ意味がある」と語っています。
フジテレビのドラマ制作部門で培ってきた経験を活かし、本作では若手の才能を積極的に起用。
“リアルな青春”と“フィクションのときめき”のバランスを追求し、全世代に響く作品づくりを目指しました。
音楽・編集などのスタッフが“物語の感情を支える”役割
物語の表層だけでなく、その“感情の奥行き”を支えるのが、音楽や編集といった裏方のクリエイターたちの仕事です。
映画『隣のステラ』では、登場人物の心理や関係性の微細な変化が、視覚・聴覚の両面から丁寧に表現されています。
まさに彼らの仕事が、観客の感情を揺さぶる“余韻”を生み出しているのです。
音楽:王舟が紡いだ青春のリズム
劇伴(サウンドトラック)を担当したのは、シンガーソングライターでありながら映像音楽にも精通する王舟(おうしゅう)さん。
彼の音楽は、都会的でありながらどこか懐かしさを感じさせる独特の空気感があり、本作の“隣人同士のもどかしい関係”と絶妙にマッチしています。
台詞のない場面でも感情を導く力を持つ音楽が、青春の揺れ動く心情に寄り添っています。
編集:スナディ翔子が描いた青春のテンポ
編集を担当したのは、若手映像クリエイターとして注目されるスナディ翔子さん。
本作では、カットの繋ぎやリズムに細やかな感覚が反映されており、“余白を残す編集”によって、登場人物の葛藤や間の美しさが際立っています。
何も語らずとも伝わる映像表現は、編集者の高い技術とセンスがあってこそ成り立っています。
映画『隣のステラ』スタッフ・監督情報|フジテレビ制作陣の想いまとめ
映画『隣のステラ』は、監督・脚本・音楽・編集といった全スタッフが一丸となって生み出した青春恋愛映画の秀作です。
そこには、“王道だけど今風” “淡いけれどリアル”というテーマを成立させるための、各クリエイターの繊細なこだわりと挑戦が詰まっています。
まさに、観る者の「懐かしい初恋の記憶」にそっと触れてくれるような作品に仕上がっていると感じました。
特に印象的なのは、フジテレビ制作陣が本作に込めた「まっすぐな恋愛映画を、もう一度届けたい」という強い意志です。
安易な脚色や過度な演出に頼らず、シンプルな感情を丁寧に描き出すことを優先した点は、いまの映像作品では逆に新鮮です。
原作ファンにも初見の観客にも愛される作品として、長く語り継がれる青春映画となることは間違いありません。
この記事のまとめ
- 映画『隣のステラ』の制作陣による想いとこだわり
- 監督・松本花奈の“原作再現”への繊細な演出
- 脚本・川滿佐和子が描く“初恋のリアルな距離感”
- 原作者・餡蜜が語る創作のきっかけと喜び
- プロデューサー・岡田翔太の“王道ラブ”への挑戦
- 音楽・王舟が支える感情の余韻と映像美
- 編集・スナディ翔子が生む“青春のリズム”
- フジテレビが仕掛ける“新しい王道恋愛映画”の形

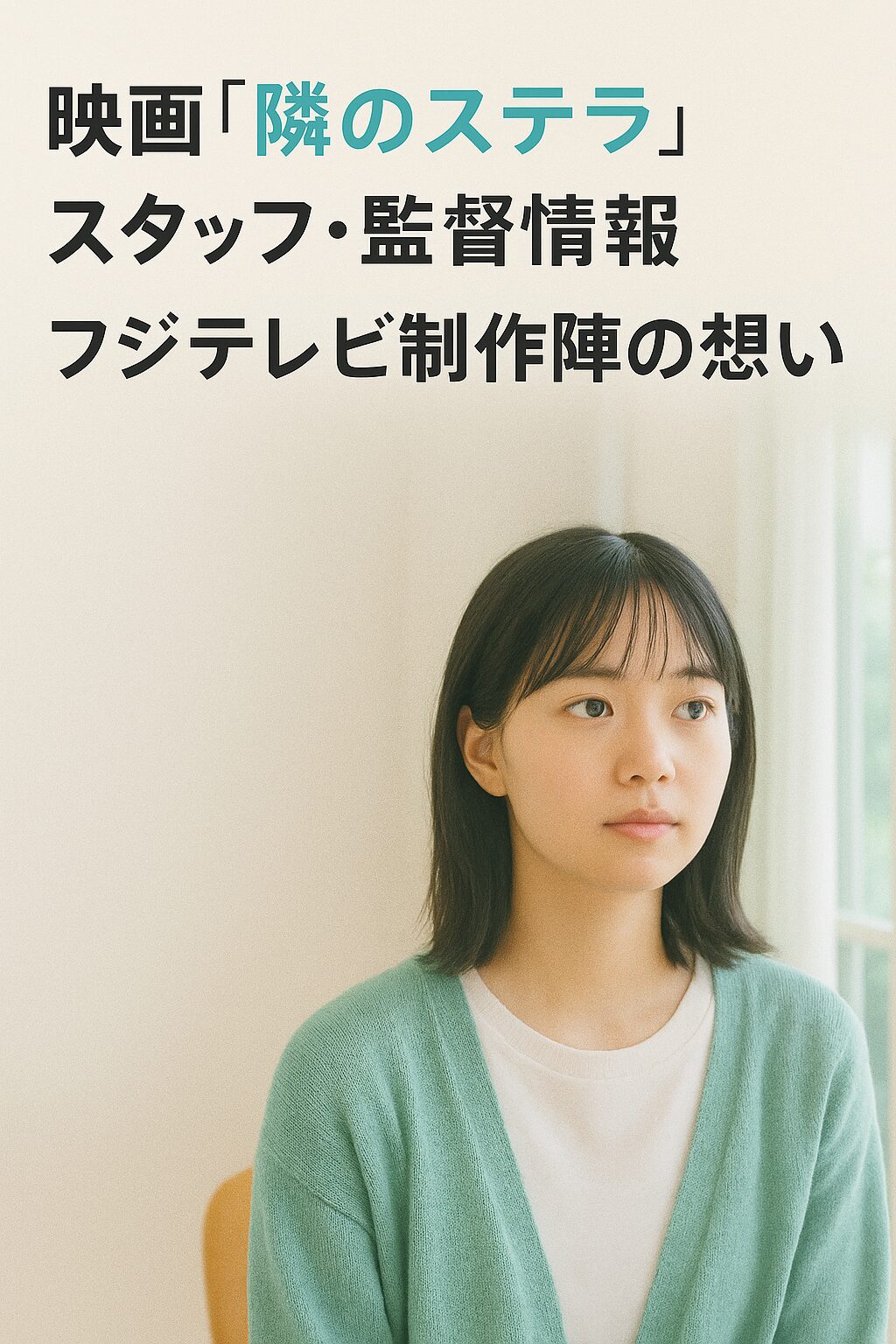


コメント