この記事を読むとわかること
- 映画『入国審査』に込められた実話の背景
- 監督の体験が脚本・演出にどう活かされたか
- 同様の体験を持つ人々との共通点とリアリティ
スペイン発心理サスペンス映画『入国審査』(原題:Upon Entry)は、ニューヨーク空港での“密室尋問”を描いた、まさに実話ベースの物語です。
本作の監督コンビ、アレハンドロ・ロハス&フアン・セバスチャン・バスケスが実際に経験した“屈辱的な入国審査”が、そのまま映画の構成と緊張感に反映されています。
この記事では、彼らが体験した本当の出来事に焦点を当て、その背景と映画にどのように織り込まれたかを深掘りします。
監督が経験した“屈辱的入国審査”の実話とは?
映画『入国審査』の原点には、監督アレハンドロ・ロハスが実際に体験した“入国時の尋問”があります。
彼はかつて、ベネズエラからスペインに移住する際、スペインの空港で思いもよらない長時間の取り調べに遭遇しました。
何の違法性もない入国手続きで、別室に呼び出され、あらゆる質問を浴びせられたというのです。
このときロハス監督が感じたのは、“疑いの目で見られ続けること”の苦痛でした。
警察や審査官の視線が、「何かやましいことがあるのでは」と決めつけるようなものであり、言葉では説明しきれない“排除される恐怖”があったと語っています。
当時スペイン語しか話せなかったロハス監督は、英語も通じない中で身振り手振りで訴えながら、自分の“存在そのものが疑われている”ような孤独感に包まれていたそうです。
この経験が、映画の主要シーンである「言葉の壁×疑念×沈黙」の構図へと昇華されました。
実体験から脚本へ──映画に落とし込まれたエピソード
監督の体験は、単なる着想にとどまらず、脚本の細部にまでリアルに反映されています。
とくに印象的なのは、「部屋に閉じ込められたまま、理由を知らされない時間の経過」です。
監督は実際に、何時間も狭い部屋に座らされ、誰も説明をしてくれず、ただ時間だけが過ぎていく不安にさいなまれたと語ります。
この「時間の密度」は映画内でも見事に表現され、観客自身も一緒に“待たされる感覚”を共有するような構成になっています。
また、尋問中に使われる質問の言い回しやトーン、言葉の選び方ひとつが“圧迫感”として作用している点も、実体験がベースになっています。
脚本では、「Yes / No だけでは答えられない曖昧な質問」が意図的に使われており、
観客もまた「自分だったらどう答えるか…?」と考えずにはいられない構造です。
こうした緻密な問いの構成こそが、本作の異様な緊張感を支える根幹になっています。
リアルが生むサスペンス──演出とキャストへの影響
『入国審査』のリアリティは、脚本だけでなく現場の演出方法にも色濃く表れています。
監督たちは撮影前、キャストに対して自らの入国体験の詳細を共有。
「無言の圧力」や「自分が“悪者”にされた感覚」を伝え、心理的なトーンを統一することで、より緊迫した空気を作り出しました。
とくに主演のブルーナ・クッシとアルベルト・アンマンには、“何をされるかわからない状況での人間の反応”を自然に演じてもらうため、あえて一部のシーンでは台本にない即興の対話も取り入れたといいます。
この工夫により、観客はキャラクターの“動揺”や“ためらい”を肌で感じることができます。
また、演出の要とも言えるのが“間”です。
台詞と台詞の間に生じる「沈黙」が、そのまま心理的な圧力として作用するように設計されています。
これは監督が実際に尋問で味わった“答えを急がされることなく、ただ見つめられる恐怖”を再現したもので、極限まで緊張を高める演出となりました。
同様の体験を語る他の移民/旅行者の証言
監督の体験は決して特殊なものではなく、世界中で同様の入国審査に苦しんだ声が上がっています。
SNSや海外フォーラムなどでも、「ただの観光だったのに別室に連れて行かれた」「なぜ質問されたのかいまだにわからない」といった証言が散見されます。
とくに中南米、アジア、中東など、国籍によって「無意識のバイアス」を受ける例は多く、
「空港で荷物を開けられ、滞在先や連絡先まで問い詰められた。観光でもストレスを感じる」(米国ビザ取得経験者の声)
こうした証言に共通するのは、「自分は疑われる側にいる」と突然自覚させられる感覚です。
そして、それが『入国審査』という映画の緊張感と深くリンクしている点も見逃せません。
もちろん、すべての入国審査官が高圧的なわけではありません。
本作が描くのは“制度そのものが持つ構造的な不安感”であり、そこに現実の体験が重なることでリアルなサスペンスが生まれたのです。
まとめ|実話が生む“問いと緊張”の本質を読み解く
『入国審査』は、監督自身の実体験から生まれた、リアルで静かな恐怖に満ちた心理サスペンスです。
“入国審査”という誰もが通る場面に潜む、見えない緊張や不公平さを、じっくりと描いています。
それは、特定の国や制度を批判するのではなく、制度そのものが持つ“目に見えない圧力”の正体に光を当てた作品とも言えるでしょう。
観客はスクリーンの前で、ただ見ているだけではいられません。
「もし自分だったらどう答える? 何を隠してしまう?」と、無意識のうちに自分の内面と対峙することになります。
そしてそれこそが、この映画の問いかける本質。
たった一つの質問が、信頼・人間関係・人生までも揺るがす――。
その緊張と違和感を、自分自身の感覚でぜひ体験してみてください。
この記事のまとめ
- 映画『入国審査』は監督の実体験が基になっている
- “理由なき尋問”と“沈黙の圧力”が脚本に反映
- 演出面でもリアリティを重視し、緊張感を演出
- 他の移民や旅行者も同様の体験を語っている
- “問い”が生む心理的サスペンスの本質に迫る

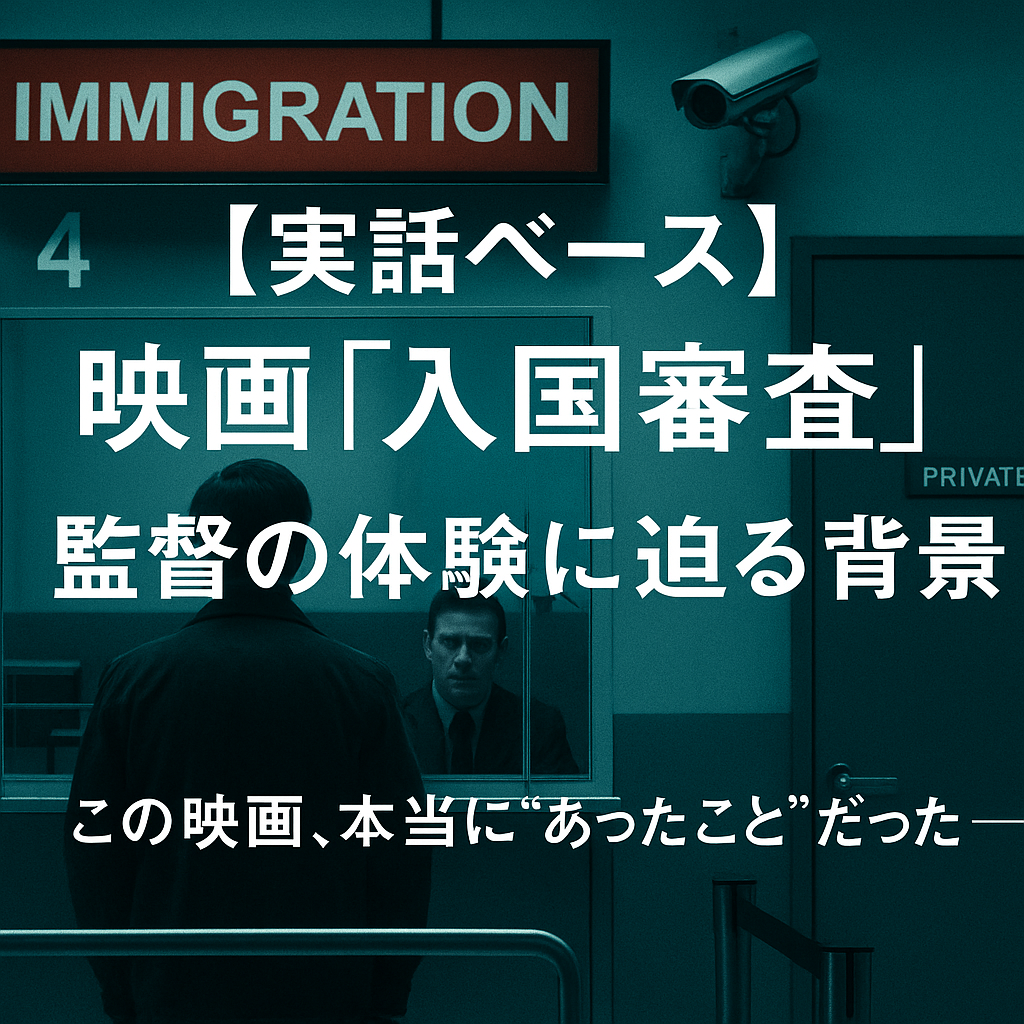
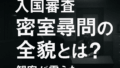

コメント