この記事を読むとわかること
- 『アマデウス』で使用された主要な楽曲とその場面
- モーツァルトの音楽が物語と感情表現に果たす役割
- 音楽監督の意図や選曲の意味から読み解く演出
映画『Amadeus』(1984年公開)は、モーツァルトの人生とサリエリとの対立を描いた作品であり、そのドラマ性を劇的に支えているのが音楽です。オープニングの高揚感ある交響曲からラストシーンの静謐なレクイエムに至るまで、劇中には印象的なテーマ曲や旋律が数多く登場します。この記事では、オープニング/テーマ曲/ラストシーンで使われた楽曲を中心に、そのシーンとの関係や演出意図を丁寧に紐解いていきます。
オープニングの楽曲:最初に観客を引き込む一音
映画『アマデウス』の冒頭は、交響曲第25番 ト短調 K.183の緊迫した旋律から始まります。
わずか数秒で観客をモーツァルトの世界観に引き込むこの楽曲は、映画全体のテンションと情緒の方向性を見事に設定しています。
「ただの伝記映画ではない」と感じさせる鮮烈なオープニングです。
交響曲第25番 ト短調 K.183 — 劇の始まりを告げる緊張感
この交響曲は、モーツァルトがわずか17歳で作曲した作品でありながら、激情的で重厚な響きが特徴です。
映画ではサリエリの絶叫とともに、この交響曲が流れ始め、彼の苦悩と物語の幕開けが印象付けられます。
この瞬間に観客の「耳」が物語の語り部となるのです。
ヴィジュアルと音楽の調和:シーン構成の工夫
オープニングでは、雪の中を駆ける召使いたちの足音と、モーツァルトの音楽が完璧にシンクロしています。
映像と音が互いを補完しあいながら、物語が静かに、しかし確かに動き始めていることを感じさせる構成です。
演出面では、音楽がナレーションやセリフに代わる“情感の装置”として使われています。
中盤に刻まれるテーマ曲と再登場するモチーフ
物語が進むにつれて、『アマデウス』ではモーツァルトの代表曲が巧みに挿入され、キャラクターの内面や社会的な立場を描く役割を果たします。
中盤では、宮廷での権力構造や作曲家同士の駆け引きが音楽によって語られていきます。
ここでは、劇中で何度も印象的に使われる“モチーフ”に注目してみましょう。
歓待の行進曲(March of Welcome)と宮廷の対比
皇帝によって用意された形式的な行進曲は、モーツァルトの初登場シーンで使用されます。
しかしその直後、モーツァルトがそれを茶化すように即興で演奏し直すことで、彼の自由奔放さと創造性が際立ちます。
音楽そのものが「反骨」と「風刺」の象徴になっているのです。
Figaroのマーチ/Non più andrai — 社交と風刺の象徴として
オペラ『フィガロの結婚』の中から「もう飛ぶまいぞこの蝶々」が使用される場面では、宮廷内の社交的虚飾と庶民感覚の対比が強調されます。
この曲は繰り返し登場し、モーツァルトの挑戦的な姿勢と、サリエリの心のざわめきを映し出しています。
このように、音楽が一種の心理描写やドラマの装置として機能しています。
ラストシーンとテーマ曲:終幕に込められた意味
『アマデウス』の終盤では、レクイエム K.626の旋律がドラマチックに響き渡り、物語を締めくくる情感を極限まで高めます。
死を前にしたモーツァルトと、罪悪感に揺れるサリエリという対比が、音楽によって痛切に浮かび上がります。
言葉よりも音楽がすべてを語る、象徴的なクライマックスです。
レクイエム K.626 — Confutatis や Lacrimosa の使いどころ
モーツァルトの遺作として知られるレクイエムは、死と贖罪、そして創造の美しさを象徴しています。
Confutatis の激しさと Lacrimosa の哀しみが交互に押し寄せる中で、観客は彼の死をただ“見る”のではなく、“聴く”のです。
音楽が遺言となり、人生そのものを奏でる瞬間といえるでしょう。
ピアノ協奏曲 第20番の楽章 — 静かな余韻と昇華
エンディングでは、ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K.466の旋律が静かに流れます。
これはサリエリの“勝利”ではなく、モーツァルトの魂が昇華していく演出です。
映画全体がモーツァルトの才能を讃えるレクイエムとなっていることを、この終幕の選曲が象徴しているのです。
なぜこの楽曲が選ばれたのか:演出家と作曲家の狙い
映画『アマデウス』の音楽選定は、単なるクラシックBGMとしてではなく、ストーリーそのものを“語る言葉”として機能しています。
選ばれた楽曲にはすべて明確な意味があり、登場人物の感情や社会構造、さらには時代の空気感までも表現しています。
その意図を読み解くことで、映画の理解は格段に深まります。
Neville Marrinerによるサウンドトラック制作の背景
本作の音楽監督を務めたのは、イギリスの名指揮者ネヴィル・マリナー。
彼はモーツァルトの楽曲を「映画の一部として再構成」するという考えのもと、場面に合うテンポや演奏ニュアンスを細かく調整しました。
その結果、ただの“名曲集”ではなく、物語と一体化した音楽演出が実現されました。
音楽がキャラクター心理を描くカタチ
モーツァルトが曲を“感じている”場面、サリエリが“嫉妬する”場面、皇帝が“無関心である”場面など、すべてに音楽が対応しています。
特に、感情がセリフで語られない場面こそ、音楽が登場人物の“内面の声”として存在している点は見逃せません。
音楽が心理描写の代弁者になっている映画──それが『アマデウス』なのです。
まとめ:音楽が『アマデウス』にもたらす余韻と思索
『アマデウス』は、モーツァルトとサリエリの人生を描いた伝記映画であると同時に、音楽そのものを語り手とする異色のドラマです。
台詞や映像だけでなく、音楽が登場人物の感情や物語の構造を織りなす軸となって機能しています。
それゆえに観終わった後も旋律が記憶に残り、深い余韻とともに思索を促すのです。
クラシック音楽が「物語」として響く
映画に使われた曲の多くは、既に知られているクラシックの名曲ですが、『アマデウス』という物語を通すことでまったく新たな文脈を与えられています。
それはまるで、楽曲が“語り直されている”ような体験。
音楽の聞こえ方さえも変えてしまう映画、それがこの作品の最大の力です。
映画を通じてクラシックに触れる入口に
クラシックに馴染みのない人にとっても、『アマデウス』は音楽との距離を縮める最良の入り口となります。
単なるBGMではない、“語る音楽”を通して物語に入り込む体験ができるのです。
音楽の持つ力を再認識させてくれる、永遠の傑作──それが『アマデウス』です。
この記事のまとめ
- 映画『アマデウス』は音楽が物語を語る作品
- オープニングには交響曲第25番を使用
- 中盤ではモチーフがキャラの心理を表現
- ラストシーンでレクイエムが深い余韻を残す
- 楽曲は意図的に選ばれ物語と一体化している
- 音楽監督ネヴィル・マリナーの演出も重要
- サリエリの視点が音楽の意味を増幅
- クラシック初心者にも強く印象に残る構成



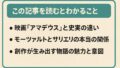
コメント