この記事を読むとわかること
- 映画『アマデウス』ラストの意味と象徴性
- モーツァルトの死因に関する有力な歴史的説
- 映画が史実を超えて描いた心理ドラマの構造
映画『アマデウス』は、モーツァルトとサリエリの才能と嫉妬の物語を軸に展開しますが、クライマックスのラストシーンとモーツァルトの最期には、数々の謎と解釈の余地が残されています。
本記事では、映画版のラストが何を意味しているのかを読み解くとともに、実際のモーツァルトの死因についての諸説を比較・考察します。
「映画の中の死」と「歴史的事実」のギャップをつなぎながら、あなたの観賞後の疑問を解消できるような解説を目指します。
映画『アマデウス』のラスト:最後に描かれる意味とは?
『アマデウス』のラストシーンは、精神病院に収容された老サリエリが、他の患者たちを「凡庸の守護聖人」として赦すという異様で印象的な場面で幕を閉じます。
モーツァルトの狂気じみた笑い声が響き渡る中で終わる演出には、観客の心に「何が真実なのか」を考えさせる余韻が強く残ります。
このラストが象徴するものを読み解くことで、本作の核心に近づくことができます。
最後の「笑い声」とサリエリの告白
物語の最後、老サリエリが語り終えた後に聞こえてくるモーツァルトの笑い声は、死者の嘲笑なのか、サリエリの幻聴なのか、はたまた観客へのメタ的な問いかけなのか、多義的です。
この笑い声は、凡庸な人間の傲慢や妄想を一蹴するような存在として描かれる“天才”モーツァルトの象徴としても捉えられます。
サリエリの“罪の告白”が真実であるかどうかは曖昧であり、観客に委ねる構造になっているのも、この映画の特徴です。
「凡庸の守護者」としての自己定位
ラストでサリエリは「凡庸な人々の守護聖人」と自称します。
これは、自らの平凡さを受け入れた上で、それを肯定しようとする“救い”の姿勢とも解釈できます。
一方で、“凡庸であることへの開き直り”でしかなく、神に選ばれなかった者の屈折したプライドとも読めます。
この両義性が、サリエリというキャラクターの奥深さを際立たせています。
観客に託す解釈の余地と曖昧性
『アマデウス』の終幕は、決して一つの結論を押しつけるものではありません。
語り手が“信用できない人物”であることも、この曖昧さを助長しています。
観客は、「サリエリの告白」をどこまで信じるべきかを自ら判断しなければならず、それが作品への没入感を生み出しているのです。
映画が提示する死因:サリエリによる“毒殺”説?
映画『アマデウス』では、モーツァルトの死因について明言されていないものの、サリエリによる“毒殺”の可能性が強く示唆されています。
この設定は、歴史的事実とは異なるフィクションとしての大胆な演出でありながら、多くの観客に衝撃を与える演出効果をもたらしています。
ではなぜ、映画はあえて“毒殺”という要素を導入したのでしょうか?
映画中の暗示と演出による“殺害”構図
映画では、黒装束の男がモーツァルトのもとを訪れ、レクイエムを依頼します。
この男の正体が最後まで明かされないことにより、観客の不安と疑念を巧みに煽る構造になっています。
実際にはサリエリが背後にいるという事実が、後半で明かされることにより、「モーツァルトを精神的に追い詰めた者」としてのサリエリの罪が明確になります。
告白という語りの信憑性と信用できない語り手
重要なのは、この物語があくまでサリエリの回想=主観的な物語である点です。
つまり、「毒殺」説も含め、サリエリ自身が語ることのすべてが、真実かどうかは明らかにされていません。
観客は、サリエリの告白が贖罪の誇張なのか、それとも狂気に支配された妄想なのかを想像するしかありません。
フィクションとしての創作意図とドラマ性
脚本家ピーター・シェーファーは、インタビューの中で「史実ではなく“神と人間”の関係性を描きたかった」と語っています。
毒殺説はサリエリの内面にある神への反逆の象徴であり、モーツァルトの死は、サリエリの破滅的な信仰心の果てとして描かれているのです。
結果として、映画は史実を越えた「芸術的真実」に到達していると言えるでしょう。
歴史的にはどう死んだのか?モーツァルトの死因諸説
映画『アマデウス』では死の原因が曖昧に描かれ、「毒殺説」が物語上の中心テーマとして用いられました。
しかし、実際のモーツァルトの死因には、さまざまな医学的・歴史的な仮説が存在します。
以下では、過去に有力とされてきた主な死因説を紹介し、その信憑性を考察します。
腎臓病・急性腎炎(糸球体腎炎)説
最も有力とされているのが「急性糸球体腎炎による腎不全説」です。
死の直前に報告されたモーツァルトの症状──むくみ(浮腫)、嘔吐、発熱など──が、腎臓機能の急激な低下と一致するとされています。
この説は、現代の医師による症例分析にもとづいており、科学的根拠が比較的強い仮説といえるでしょう。
リウマチ熱・ストレプトコッカス感染説
モーツァルトは少年期にリウマチ熱を何度か患っており、これが晩年に再発した可能性も指摘されています。
溶連菌感染が腎臓や心臓に合併症を引き起こしたとする医学的な分析も存在します。
これにより、心不全や全身衰弱へと進行した可能性があり、毒物ではなく自然疾患による死を裏付ける説です。
他の仮説:毒、梅毒、水銀中毒など
毒殺説以外にも、梅毒や水銀中毒、慢性うつ、自己破壊的な生活習慣といった要因が複合的に作用したとする説もあります。
梅毒治療に使用されていた水銀が体に蓄積した可能性や、精神的ストレスによる免疫低下も一因として挙げられることがあります。
ただし、これらはいずれも決定的な医療記録が存在しないため、仮説の域を出ません。
なぜ正確には明らかでないのか
モーツァルトの死に関しては、解剖記録や詳細なカルテが残されていません。
また、葬儀も質素に行われ、埋葬地も不明確なため、現代的な法医学による検証ができない状況です。
そのため、今後も新しい文献やデータが発見されない限り、「死因の真実」は永遠の謎として残り続けるでしょう。
映画と史実の間:なぜこのラストを選んだのか?
『アマデウス』のラストが歴史的事実に忠実ではないことは多くの視聴者が認識しています。
それでも、この劇的なフィクションの結末が、多くの人の心に強く残る理由は何なのでしょうか。
この章では、映画が“事実”ではなく“象徴”を選んだ理由を考察していきます。
心理ドラマとしての構成意図
映画『アマデウス』は、あくまでサリエリの内面世界に焦点を当てた心理劇・人間ドラマとして構成されています。
そのため、史実の再現よりも、感情の流れや葛藤のリアリティを優先する構成がとられています。
サリエリの嫉妬・信仰・罪悪感という複雑な内面を描くには、「毒殺」や「自責の念による狂気」という象徴表現が最適だったのでしょう。
「天才と凡才」の対比がもたらす象徴性
モーツァルトとサリエリの物語は、「才能の不平等」という普遍的なテーマに根ざしています。
「なぜ神は私ではなく、あの軽薄なモーツァルトに才能を与えたのか?」という問いは、多くの人が人生で一度は感じる感情でもあります。
この痛みの普遍性を描くために、史実よりも象徴的なストーリー展開が選ばれたのです。
観客の解釈を重視するラスト構造
この映画のラストが強く評価されているのは、「観る者に問いを残す構造」になっているからです。
サリエリの語りは真実だったのか?モーツァルトは本当に殺されたのか?彼らの音楽の本質とは何か?
そのすべてが“答えのない問い”として提示されることで、観客はただ消費するのではなく、能動的に作品と向き合うことになります。
まとめ:『アマデウス』の終焉とモーツァルトへの賛歌
映画『アマデウス』は、単なるモーツァルトの伝記映画ではありません。
それは、天才と凡才、神と人間、芸術と嫉妬という普遍的なテーマを描いた、壮大な心理ドラマであり、人間の本質に迫る寓話です。
そのラストとモーツァルトの死因の描き方こそが、作品全体に深みと余韻を与えているのです。
映画ラストの核心と余韻
老サリエリが「凡庸の守護者」として他の患者たちを赦すラストは、皮肉と諦念、そして静かな狂気が入り混じる印象的な幕引きでした。
響き渡るモーツァルトの笑い声は、天才が死んでもなお、芸術として生き続ける力を象徴しています。
この終わり方があるからこそ、観客は問いと余韻を胸に作品を振り返ることになるのです。
歴史的死因とは異なる映画的命題
実際のモーツァルトの死因は、腎疾患や感染症による自然死の可能性が高いとされています。
しかし映画ではあえて“毒殺”の暗示を採用することで、サリエリの内面の葛藤や、才能に対する人間の無力さを強調しています。
事実を超えた表現によって、より深い真実に迫る──それが本作の芸術的意図と言えるでしょう。
観る者に残る問いと感情
『アマデウス』を観終えた後に残るのは、「自分は凡庸であることをどう受け入れるか」という問いかもしれません。
また、「芸術とは誰のためにあるのか」「神は誰に才能を与えるのか」という大きなテーマにも心を揺さぶられます。
この作品は、単なる物語以上に、私たちの人生観や価値観にまで影響を与える力を持っています。
この記事のまとめ
- 映画『アマデウス』のラストシーンの意味を解説
- サリエリによる毒殺説はフィクションの演出
- モーツァルトの死因は医学的に諸説存在
- 史実と映画の違いから演出意図を読み解く
- 芸術と凡才の葛藤を描く心理ドラマとしての魅力
- 観客に解釈を委ねる余韻ある構成が特徴



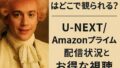
コメント